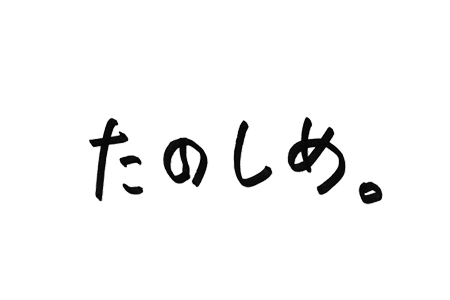形より、中身が大事。
本の修理、修復は、
中身を守るための仕事。
製本工房リーブル 代表 製本家
岡野暢夫
知識や知恵、言葉や図版、絵や写真。
人間が想像し、創作する
あらゆるイメージを写し取ったその紙を、
幾重にも折り畳み、束にした物をさらに綴じ込み、
カバーで挟み、包んで、
一冊の塊にまとめていく製本工芸の世界。
心ある製本家は、そんな本への愛情を形にする一方で、
時の荒波にさらされて、擦れ、破れ、
傷んだり壊れたりした本たちを、慈愛の目で繕い、
可能な限り元の状態に戻していく。
カッター、ハサミ、定規、へら、
製本針、竹ユビワ、刷毛、ピンセット、
革包丁、プレス機などなど。
さまざまな種類の紙や糸、布地、革を使って
糊付けられた本を、一枚一枚解体し、
修理から修復まで丹念に対応するので、
自然と道具の種類も多様になる。
工芸はすべて、形をつくる芸術。
ところが製本工芸だけは、大切なのは本の「中身」。
形は二の次なのだよ、と製本家はつぶやく。
すると本の修理修復も、形を直しながら、
中身を守っているわけだ。
文・内野一郎
写真・渡辺真一

鍋や釜に穴が開いたって
メンテナンスしながら使う。
それが、江戸の美学。
板橋区立エコポリスセンター「現代のいかけやさん」
関根 守雄
ラジオを作ったり、直したりするのが、
子どもの頃から好きだった。
働き出してからは、
建築現場の仕事で長く生きてきた。
やがて定年を過ぎ、さてこれから何をしよう?
と、世間を眺め渡していた時に目に入ったのが、
「現代のいかけやさん」の募集だった。
鋳掛屋(いかけや)とは、大量消費の時代に珍しい。
そんな好奇心も働いて、この活動に加わった。
物資の量も、材の数も限られていて、
壊れたら直すのが当たり前の、江戸から昭和。
鍋、釜などの生活必需品である鋳物修理は、
庶民の暮らしに無くてはならぬ存在だった。
リサイクル&リユースの現代に復活し、
鍋、釜、薬缶にはリベットを使った穴塞ぎ、
多い時には日に40本に上る刃物研ぎ、
傘直しやご婦人たちの靴のかかと修理まで。
できるものは、幅広く請け負っている。
職人仲間は、皆さん80代。年の割に頑張ってるよ。
お客さまは主婦が多いね。地方から電話をくれて、
遠路わざわざ訪ねてくる方も珍しくない。
使い続けてきた物には心が宿るし、愛着が湧くからね。
大切にメンテナンスしながら、長く一緒に居たいんだ。
その気持ちがよくわかる。
文・内野一郎
写真・渡辺真一

1機、約40年。
技術力と想像力で、
航空機を予防整備し続ける。
株式会社JALエンジニアリング アビオニクス整備マイスター
田中滋之
航空機は、機種が設計された時点で、
固有のメンテナンスプログラムも出来上がっている。
逆に言えば長い期間のメンテナンスを考えて
部品設計されている、
ロングライフ思想に支えられた乗り物だ。
JALグループだけで毎日約1,000便が空を飛び、
10数万人のお客さまを運んでいる。
それら機体のメンテナンス期間は、
1機種の初号機から最終号機退役までの約40年。
アビオニクス整備マイスターは、
自動試験装置「ATE(Automatic Test Equipment)」を使い、
航空機の飛行をコントロールする
大切な電子部品のチェック、メンテナンスを行う。
機体に付いた傷は目に見えることが多いが、
電子部品の故障は目に見えない。
そこで仮説を立ててトラブルシュートし、
多様な計測器を駆使し、
故障個所を絞り込んでいくことになる。
現在のトラブルや故障を直すだけでなく、
航空機が飛んでいる状態を想像し、
今後トラブルを起こしそうな箇所を見つけて、
予防整備しておくことが重要なのだ。
目に見えない場所のメンテナンスこそ、
お客さまのかけがえのない安心を生み出している。
文・内野一郎
写真・渡辺真一

何百万回の開閉と、
安全を維持するための
自動ドアのメンテナンス。
日本自動ドア株式会社 全国メンテナンス本部 エリアマネージャー
樫原宏尚
自動ドアは、大きく分けて、
ドア、自動開閉装置、センサの
3つの機能から出来上がっている精密機器。
心臓部は、ドアを吊り、
センサと連動してドアを動かす、
ドア上に設置された、1本の自動開閉装置だ。
自動ドアの修理、メンテナンス作業の大半も、
この自動開閉装置がメインになる。
長い走行レールを包む点検カバーを外すと、
モーター、減速機、駆動・従動ブーリ、歯付きベルト、
制御器、吊車などの部品と装置が整然と現れる。
建築物の出入り口を始めさまざまな場所で、
何百万回と開閉を続けるうちに、故障も発生する。
そんな自動ドアの保守とメンテナンスを、
樫原さんは、日本自動ドアに入社以来17年間、
東京だけで13,000台手がけてきた。
数多くの開閉による部材の摩耗や劣化、
設置環境と使用状況における耳障りな異音の相談が
実は一番多いと言う。
センサやIoTの進化とともに
自動ドアも新しい時代に入っているが、
世界中で、日本が最も進んでいる国だそうだ。
ローマ帝国の属州だった古代エジプトで、
蒸気の力と水の重さの移動で自動開閉する扉が
誕生してから、およそ二千年が経つ。
文・内野一郎
写真・渡辺真一

温泉施設の研磨再生だけは
誰にも負けない。
その自負で生き抜いてきた。
有限会社日本クリーンサービス 代表取締役
飛松繁人
御影石、大理石、伊豆石、若草石、十和田石。
温泉の床や壁、大浴場には、
実に様々な石が使われている。
その特殊空間を形作る素材の美観維持には、
清掃と洗浄だけでは限界がある。
という思いがどうしても拭い切れず、
試行錯誤し、研究と改良を重ね、
遂に辿り着いた方法が、研磨再生だった。
思い返せば、研磨との出合いは10代の頃。
厨房製造会社への就職でステンレス研磨を知り、
後に転職したボウリング場で
ボールのプラグ(穴空け)後の研磨を学び、
都内有名ホテルの支配人に
石材のメンテナンスが難しいと教えられ、
すぐさま清掃会社を興すと
墓石屋の親父さんに残材の黒御影石を分けてもらい、
独学夢中で石の研磨に挑み続けてきたのだった。
研磨再生は環境と素材に優しい。
独自の技も生み出した。
温泉の本場箱根に拠点を構え、
箱根小涌園ユネッサン、天悠を始め、
日本各地の温泉施設を研磨再生してきた。
研磨再生の達人。
いつしか、そう呼ばれるようになっていた。
文・内野一郎
写真・渡辺真一

古ぼけた革グラブの再生が、
野球への情熱も
新品のように生まれ変わらせる。
サンスポーツ取手本店「寺田工房」 代表取締役
寺田陽一
白球を投げ、バットで打ち、グラブで受け止める。
ただこれだけのシンプルな野球というスポーツが、
今も日本人の心を魅了し続ける。
そのわけを考えてみると、
そこにはスポーツゲームの面白さだけではなく、
道具愛という精神が、
深く大きく作用しているのではないだろうか。
寺田さんはこの野球に欠かせない道具の一つ、
「グラブ」の再生修理で
世界的に見ても新しい独自の市場を開拓した。
きっかけは息子が小学校から大学4年間、
野球をやったこと。
使い込まれ、磨耗し、革もひび割れ、
傷や穴もできすっかり色褪せたグラブを見て、
ある日、オーバーホールを思いつく。
ボロボロになったグラブを
じゃぶじゃぶと水で洗うことから始め、
周囲は驚愕し、目を剥いた。
怯まずにグラブを解体し、破損した指袋を交換し、
表革を研磨し、革を染め直し、革を補強し、
紐を組み直し、成型し、約12年の失敗と研鑽。
古ぼけたグラブを新品同様に蘇生させる
寺田式のグラブ再生術を確立させていった。
父に買ってもらった形見のグラブ、
災害で泥だらけになったグラブ、
かつて甲子園で闘ったグラブ、
それぞれの思いと記憶を宿したグラブたちが、
息を吹き返すために
今日も日本中から集まり続けている。
文・内野一郎
写真・渡辺真一

自然循環する
環境メンテナンスの中で
楽しむゴルフ、
そんな時代が始まっている。
株式会社嵐山カントリークラブ
取締役 グリーンキーパー
前花 貢
嵐山カントリークラブ(埼玉県)は、
第56代・57代内閣総理大臣を務めた
あの岸信介が初代会長となり開かれた、歴史あるゴルフ場。
そんなグリーンの聖地で、ゴルフコースの命とも言える、
芝生の革命が始まっている。
主人公は、鹿児島大学農学部を卒業後、
公務員を経てグリーンキーパーになった、
異色の経歴を持つ前花貢さん。
彼は、日本中のゴルフ場で当たり前のように行われてきた
化成肥料や除草剤、殺菌剤の使用、
機械による転圧で土を固める手法など、
いわゆるこれまでの「常識」を疑った。
では、自然の中で楽しむゴルフコースに必要な元気な芝を育て、
維持していくために重要なこととは、いったい何か?
彼はそれを、芝の土壌に生きる、
微生物を活性化させることだと見抜いた。
そのために考案した方法が、
なんと「米ぬか」を定期的にグリーンに散布すること。
米ぬかが散布されると、それを食べた微生物が
生き生きと活動しはじめ、その結果、
土壌自体の密度が増し、土が詰まってくる。
つまり微生物が活発に増えると芝の根が土壌に絡み、
土の表面にコンパクションが出てくるので、
もう機械で転圧して土を固める必要はない。
前花さんの発想と実践は、これに留まらない。
希釈した海水を散布し、ミネラルで芝を活性化する。
刈った芝を捨てずに芝目に散らばし、
土壌還元していくことで芝の堆肥栄養にする。
まさにそこに生まれたのは、環境スポーツの次代をリードする、
自然循環によるグリーンの育成維持管理の世界だった。
前花哲学は広がりを見せ、
ティーイングエリアの植栽整理や、ティ周りの人工物撤去、
OBラインの見直しといった、コース使用の変化にも及んでいった。
そしてこの流れは今、グリーンキーパーの働き方改革という、
人材活用の見直しにも進み始めている
文・内野一郎
写真・渡辺真一

出航したお客さまが
マリーナに無事に帰ってくる、
それが最高の満足です。
湘南サニーサイドマリーナ株式会社
営業サービス本部 課長
山崎翔太
ボートやヨットのメンテナンスに心惹かれるのは、
年式やエンジンが古くなったからといって、
クルマのように
オーナーが気軽には乗り換えを行わない点にある
と、山崎は思っている。
祖父がこの湘南サニーサイドマリーナに
所属している艇の船長をしていた頃、
幼かった自分が見上げていた船や、
製造から30年を経た船も、
未だに現役で動いている。
そういった年代物とも向き合いながら、
時を超えたメンテナンスを手掛けられることが
この仕事の醍醐味の一つだ。
そんな船たちのメンテナンスは、
一つとして同じ作業がないばかりか、
ボルト一本の締め忘れでも、生死に関わる。
なぜなら海に出た船は、
故障しても、その辺に乗り捨てることはできない。
待っているのは漂流、遭難という最悪の事態。
だからメンテナンスを行うことは、
憶測で判断せず、すべてを自分の目で見て、
お客さまが乗る船の本質を見極めるということなのだ。
そのためにもこの世界の新人には、
船の掃除を徹底的に叩き込む。
掃除は、本質を見極めるためのトレーニングだからだ。
汚れを発見した時、なぜ汚れているのか。
汚れの根源は、どこにあるのか。
今後どうすれば、汚れずにすむだろうか。
これを常に考えて掃除をする者には、
船の本質が視えてくる。
反対に掃除ができない者には本質が視えず、
メンテナンスはできない。
たかが掃除、されど掃除なのである。
文・内野一郎
写真・渡辺真一

雨や、陽や、空気の中で、
変化していく墓石の汚れを
落とすということ。
株式会社清水屋
代表取締役社長 清水健介
明治10年創業の、
板橋区にある墓石屋に生まれて、5代目を継いだ。
学生時代から家業を手伝ってきたので、
数えてみると、
納骨回数は軽くもう1000回を越えている。
墓石にも種類があって、
安山岩、花崗岩、閃緑岩、斑レイ岩と、
成分も、性質も違う石材が、300種以上。
そんな石たちを見比べ、触れ、デザインしてきた。
お墓というのは、いま生きている、
残された人のために在るものだと感じている。
だから、墓石の汚れ落としも、
喜ぶお施主さんの笑顔が見たくて、
地道に取り組んできた。
現在、使っている
工業用ナイロンタワシに辿り着くまでには、
さまざまな素材や道具を試し、
石を研磨する「砥粒子」の粗さの加減や、
対象とする石材に合うかどうか、
ベストの型番を見つけるまでに、手間も暇もかかった。
石は空気の中で酸化し、日焼けし、
色も、風合いも変化していく。
雨などの水垢が、斑になってコーティングされ、
あるいは、石の中に含まれている鉄分が
表に浮き出て、茶けてくる。
人が齢をとるのと同じように、石も、
風雪の中で表情が変わり、齢をとっていくのだ。
お施主さんの中には、
お墓参りに来ているだけで満足で、
墓石が汚れていることにすら、気づかない人もいる。
でも自分としては、
できるだけ早い段階で、汚れを落として差し上げたい。
そうしてこの地の墓守として、
笑顔でまた来ていただけるお墓を、守り続けていきたい。
文・内野一郎
写真・渡辺真一

車いすのメンテナンスは
利用者の身体を護る、
気づきの「目」になること。
啓成会高等職業技術専門校
車いす・シーティング科講師
車いす安全整備士、シーティングエンジニア
片石 任
健常者と呼ばれる健康体を持つ者、
自分の二本の足で歩くことのできる者には、
なかなか感じられぬ世界は、確かにある。
たとえば白杖を持つ方たちの歩行に出会い、
もしその方が道路のどこかに立ち尽くして
杖を自分の頭上に高々と上げていたとしたら、
あなたは何を為すべきか。
その知識すら持ち合わせてない健常者は、
果たして社会人として健常なのだろうか。
たとえば車いすという乗り物。
歩行が困難な人、高齢者など、利用者は数多い。
車いす安全整備士でシーティングエンジニアの片石さんは、
以前は航空機整備士だったが、
思いあって職業訓練を受け、その後、
電動車いすの世界に入り、現在の仕事に就いた。
車いすに携わり11年。彼からこんな話を聞いた。
下肢が麻痺し感覚の弱い方が
身体に合わない車いすに座り続けていると、
気づかぬうちに身体に負担がかかり、
褥瘡(じょくそう/床ずれ)と呼ばれる
二次障害が起きる原因になることもあるのだそうだ。
車いすの走行機能を修理し、シートを調整し、
乗り心地を快適に維持することは、
利用者の身体の隅々までも意識して
車いすをメンテナンスし、利用者の身体を護る。
気づきの「目」になってあげることでもあるのだ。
目と言えば、
車いすに座ってみて感じる意識の変化は、
その視点の低さに現れる。
立って歩く人から見下ろされる、
視線の圧力は驚くほど強い。
だからだろう。
そんなバリアは無用なものと知る北欧などでは、
車いすのシートを操作して持ち上げ、
健常者の目の高さに合うようにして、
同じ目線で堂々と語り合う。
そこが始まりなのだ。
文・内野一郎
写真・渡辺真一