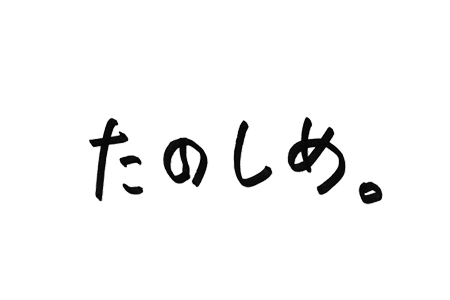午後遅めの夕方5時になんとか滑り込めた。今日は祝日だったが運良く店内はまだ人がまばらで、僕の姿に気づいてくれた支配人の若松さんが、カウンターの一番右端の席に座らせてくれた。
本駒込にある僕の会社から、帝国ホテルがある日比谷までは白山駅から都営三田線に乗って約20分の近距離だ。地下から地上までの長い階段をのぼり切ると目の前に巨大な帝国ホテルの建物が現れ、いつもながらその大きさに圧倒されつつ、ホテル正面入口ではなくサイドの入口から忍び入るようにスッと中に入った。そこが2階にあるオールドインペリアルバーまでの最短コースだ。
早朝に起きて出社し、片付いていない仕事を本人的にはテンポよくこなしているつもりなのだけれど、机に積まれた資料のファイルはいっこうに減る気配がなく、『帝国ホテル オールドインペリアルバーBOOK』の記者会見で配布する資料の紹介文を、発売前日のぎりぎりのぎりになって書いている始末だから、はたから見ると相当に要領の悪い仕事の仕方をしているのかもしれない。妻に言わせると、どうして貴方はひとつのことしかできないのか、どうして説明の仕方がいくつになっても進歩しないのか、そういったすべてを本当に治す気があるのか、本当にそんなことで外で仕事ができているのかしら。と、いまだに言われつづけている僕だから、おそらくきっと治らないのかもしれません。
そんなことを思い出しながらオールドバーのカウンター席に腰をおろして、ふうっと息を吐いた。この店のカウンター席は、これまで座ったことのあるカウンターの中でも、極上の座り心地と安堵感を与えてくれる特等席だ。
カウンターの厚みや、テーブルに肘をついた時のテーブルカーブの曲線の具合の良さはもちろん、おそらくそれ以上に気持ちを包みこんでくれているのが、カウンター席の灯だ。照度の落ちた店内で、カウンター席ごとにカウンターテーブルの目の前を円形のダウンライトが柔らかく照らし出していて、その30cmほどの円い光の空間が、それぞれ着席した者に与えられる独立したパーソナルスペースになっている。実によく考えられた設計なのだ。
店内を見渡すと、店奥のライト館の壁の前のボックス席に数名、カウンターの中央辺りに数名の客がいる。夕方6時に向かうにつれてもっと混んでくるはずだから、それを避けるためにも30分くらいで引き上げよう。
さて、カウンターの最右翼席には隠れた特典があって、カウンター席が途切れた右側に実はもうひとつ椅子があり、そこに荷物を置くことができる。これはとてもありがたい。僕はいつも割に重たいバックパックを背負っているので、それを置かせてもらった。
カウンターの中で、見知ったチーフバーテンダーの方たちが手際良く仕事をこなしていく。その姿を頼もしく眺めながら、お願いしたドライマティーニの辛さに自然と口元がゆるみ、もういちど腹の奥からゆっくりと息を吐いた。この瞬間、僕はバーカウンターから瞬間移動して、独りで木立の中の露天風呂に浸かっているような感覚の中にいる。肩から力が抜け落ちていく、このひとときが恍惚感。
腕時計を見ると20分ほどが過ぎていた。もう一杯はいけるなと思い、今回の『帝国ホテル オールドインペリアルバーBOOK』の件で何度も手紙のやりとりをさせていただいた、元支配人の伊藤多喜男さんから教えてもらった、英国式ピンク・ジンを飲んでから帰ることにした。
伊藤さんのお話では、このカクテルはあの英国首相チャーチルの相方だった党首(エバンス)に、伊藤さんが作り方を直接教えてもらい、そのレシピが今もオールドバーに残っているとのことだった。
チーフバーテンダーの塩田さんが目の前に来てくれたので、この話をした。僕は英国式ピンク・ジンをいまだに飲んだことも見たこともないので、頭の中では名前のような美しい「ピンク」色に染まったカクテルを想像していた。
ところが出てきたのは僕の想像とは大きくかけ離れていて、シェリーグラスになみなみと注がれた透明なジンと、そのなかに薄くやや紅がかった靄のような影が溶けだし揺れている。そんな「ピンク」とはとても思えない姿のカクテルだった。
「まず香りを味わってみてください」と塩田さん。
ちょっとだまされたような気持ちのまま、グラスに鼻を近づけていった。
すると途端に、なんとまあ。なんと、爽やかな香りだろう。
晩秋に早春の息吹きを嗅いだような、ぱっと晴れやかな気持ちになってしまった。
「グラスの内側にアンゴスチュラ・ビターズをまぶしまして、そこにビーフィータージンを注ぎます」
「それだけですか?」
「はい」
うむむ、伊藤さん、こんなに簡単なレシピだったのですか? しかもこのシンプルな取り合わせが、実に精妙な香りの変化を愉しませてくれています。驚きです。
イギリスは産業革命以降、技術の発展に反比例するかのように、味覚や食文化に関しては恐ろしいほど劣化していった。そんな印象を僕は持っていて、僕だけではなく皆がそう伝え合っていたように思う。実際、今から30年以上も前の話だけれど、ロンドンに行った際の夕食は十中八九、中華街で食べていた。
しかしこの英国式ピンク・ジンの味わい方には、ジンとアンゴスチュラ・ビターズが混ざり合う微妙な香りの変化と、すっきりとしたジンの味覚を、鼻腔と口腔を使って同時に愉しむ繊細さがあった。それは日本の茶や香りの文化が大事にしてきた、精妙な感覚の差を見つける愉しみにも通じ合うような気もした。英国人にはこんな味覚や嗅覚が備わっているのか。恐るべし英国文化!
「ちょっとイソジンのような香りもしますね。そのせいか、心のなかに懐かしさが立ちのぼってきて、淡い感情になります」
と塩田さんに伝えると、
「最近、ピンク・ジンを頼む方はあまりいませんが、かつての時代を感じることのできる良いカクテルだと思います。帝国ホテルのカクテルには、米軍や英軍に先輩たちが直に習って覚え、身につけてきた歴史もあるんです」と応じてくれた。
腕時計は5時50分。心も温まってきた。英国式ジェントルマンになった気分で、丸の内を歩いて帰ろう。
午後遅めの夕方5時になんとか滑り込めた。今日は祝日だったが運良く店内はまだ人がまばらで、僕の姿に気づいてくれた支配人の若松さんが、カウンターの一番右端の席に座らせてくれた。
本駒込にある僕の会社から、帝国ホテルがある日比谷までは白山駅から都営三田線に乗って約20分の近距離だ。地下から地上までの長い階段をのぼり切ると目の前に巨大な帝国ホテルの建物が現れ、いつもながらその大きさに圧倒されつつ、ホテル正面入口ではなくサイドの入口から忍び入るようにスッと中に入った。そこが2階にあるオールドインペリアルバーまでの最短コースだ。
早朝に起きて出社し、片付いていない仕事を本人的にはテンポよくこなしているつもりなのだけれど、机に積まれた資料のファイルはいっこうに減る気配がなく、『帝国ホテル オールドインペリアルバーBOOK』の記者会見で配布する資料の紹介文を、発売前日のぎりぎりのぎりになって書いている始末だから、はたから見ると相当に要領の悪い仕事の仕方をしているのかもしれない。妻に言わせると、どうして貴方はひとつのことしかできないのか、どうして説明の仕方がいくつになっても進歩しないのか、そういったすべてを本当に治す気があるのか、本当にそんなことで外で仕事ができているのかしら。と、いまだに言われつづけている僕だから、おそらくきっと治らないのかもしれません。
そんなことを思い出しながらオールドバーのカウンター席に腰をおろして、ふうっと息を吐いた。この店のカウンター席は、これまで座ったことのあるカウンターの中でも、極上の座り心地と安堵感を与えてくれる特等席だ。
カウンターの厚みや、テーブルに肘をついた時のテーブルカーブの曲線の具合の良さはもちろん、おそらくそれ以上に気持ちを包みこんでくれているのが、カウンター席の灯だ。照度の落ちた店内で、カウンター席ごとにカウンターテーブルの目の前を円形のダウンライトが柔らかく照らし出していて、その30cmほどの円い光の空間が、それぞれ着席した者に与えられる独立したパーソナルスペースになっている。実によく考えられた設計なのだ。
店内を見渡すと、店奥のライト館の壁の前のボックス席に数名、カウンターの中央辺りに数名の客がいる。夕方6時に向かうにつれてもっと混んでくるはずだから、それを避けるためにも30分くらいで引き上げよう。
さて、カウンターの最右翼席には隠れた特典があって、カウンター席が途切れた右側に実はもうひとつ椅子があり、そこに荷物を置くことができる。これはとてもありがたい。僕はいつも割に重たいバックパックを背負っているので、それを置かせてもらった。
カウンターの中で、見知ったチーフバーテンダーの方たちが手際良く仕事をこなしていく。その姿を頼もしく眺めながら、お願いしたドライマティーニの辛さに自然と口元がゆるみ、もういちど腹の奥からゆっくりと息を吐いた。この瞬間、僕はバーカウンターから瞬間移動して、独りで木立の中の露天風呂に浸かっているような感覚の中にいる。肩から力が抜け落ちていく、このひとときが恍惚感。
腕時計を見ると20分ほどが過ぎていた。もう一杯はいけるなと思い、今回の『帝国ホテル オールドインペリアルバーBOOK』の件で何度も手紙のやりとりをさせていただいた、元支配人の伊藤多喜男さんから教えてもらった、英国式ピンク・ジンを飲んでから帰ることにした。
伊藤さんのお話では、このカクテルはあの英国首相チャーチルの相方だった党首(エバンス)に、伊藤さんが作り方を直接教えてもらい、そのレシピが今もオールドバーに残っているとのことだった。
チーフバーテンダーの塩田さんが目の前に来てくれたので、この話をした。僕は英国式ピンク・ジンをいまだに飲んだことも見たこともないので、頭の中では名前のような美しい「ピンク」色に染まったカクテルを想像していた。
ところが出てきたのは僕の想像とは大きくかけ離れていて、シェリーグラスになみなみと注がれた透明なジンと、そのなかに薄くやや紅がかった靄のような影が溶けだし揺れている。そんな「ピンク」とはとても思えない姿のカクテルだった。
「まず香りを味わってみてください」と塩田さん。
ちょっとだまされたような気持ちのまま、グラスに鼻を近づけていった。
すると途端に、なんとまあ。なんと、爽やかな香りだろう。
晩秋に早春の息吹きを嗅いだような、ぱっと晴れやかな気持ちになってしまった。
「グラスの内側にアンゴスチュラ・ビターズをまぶしまして、そこにビーフィータージンを注ぎます」
「それだけですか?」
「はい」
うむむ、伊藤さん、こんなに簡単なレシピだったのですか? しかもこのシンプルな取り合わせが、実に精妙な香りの変化を愉しませてくれています。驚きです。
イギリスは産業革命以降、技術の発展に反比例するかのように、味覚や食文化に関しては恐ろしいほど劣化していった。そんな印象を僕は持っていて、僕だけではなく皆がそう伝え合っていたように思う。実際、今から30年以上も前の話だけれど、ロンドンに行った際の夕食は十中八九、中華街で食べていた。
しかしこの英国式ピンク・ジンの味わい方には、ジンとアンゴスチュラ・ビターズが混ざり合う微妙な香りの変化と、すっきりとしたジンの味覚を、鼻腔と口腔を使って同時に愉しむ繊細さがあった。それは日本の茶や香りの文化が大事にしてきた、精妙な感覚の差を見つける愉しみにも通じ合うような気もした。英国人にはこんな味覚や嗅覚が備わっているのか。恐るべし英国文化!
「ちょっとイソジンのような香りもしますね。そのせいか、心のなかに懐かしさが立ちのぼってきて、淡い感情になります」
と塩田さんに伝えると、
「最近、ピンク・ジンを頼む方はあまりいませんが、かつての時代を感じることのできる良いカクテルだと思います。帝国ホテルのカクテルには、米軍や英軍に先輩たちが直に習って覚え、身につけてきた歴史もあるんです」と応じてくれた。
腕時計は5時50分。心も温まってきた。英国式ジェントルマンになった気分で、丸の内を歩いて帰ろう。